俳優・大西信満、裏方時代に受けた“理不尽な仕打ち“。罵倒され…衝動的に「それなら表方になってやろう」

2003年、初主演映画『赤目四十八瀧心中未遂』(荒戸源次郎監督)で第58回毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞などを受賞した大西信満さん。
作品ごとに強烈な印象を与え、唯一無二の存在感を放つ実力派俳優として広く知られている。映画『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程(みち)』(若松孝二監督)、映画『キャタピラー』(若松孝二監督)、映画『さよなら渓谷』(大森立嗣監督)などに出演。
現在、Disney+にて配信中の『フクロウと呼ばれた男』、映画『東京ランドマーク』(林知亜季監督)が新宿K’s cinemaで公開中の大西信満さんにインタビュー。

◆「俺にケツを向けるな!」と罵倒され…
神奈川県で育った大西さんは、小さい頃は映画やテレビに興味を持つこともなく、とくに好きでもなかったという。
「自分の場合は、小さいときから映画が好きで映画館に通っていたとか、昔の作品をずっと見ていたとか、そういうことではまったくなかったので、芝居とか映画とか見るようになったのは、大人になってからです」
――俳優になろうと思ったきっかけは何だったのですか。
「それは今話すと恥ずかしいというか、若気の至りの部分も多分にあったんですけど…。僕は、元々裏方をやっていたんですよね。厳密に言うと特殊効果という持ち場がありまして、火薬をドカーンとやったり、ドライアイスを炊いたり…そういうことを主に音楽番組やライブでやる仕事をしていたんです。
それで、23歳頃になんとなく(仕事として)形になりそうだなというか、これなら続けられるかなと手ごたえを感じていた矢先に、もう20年以上前なので現在とは社会通念や業界の常識、人々の感覚が全然違っていた時代の話ですが、あるライブ会場で、表方の人が遅刻してきて。
たまにあることなんですけど、我々スタッフがリハーサルと仕込みを同時にやらなければならない状況になって、マイクスタンドのところに歌い手さんがいて、その間をほふく前進みたいな形でケーブルを結線していたら、突然『お前、俺に向かってケツ向けんじゃねえ!』って蹴飛ばされて。
自分なんかは末端のスタッフで、相手はその人がいなきゃイベントが成立しないわけで、どっちがいいとか正しいとかじゃなく問答無用で、全面的に自分が悪いということになって舞台監督とかにボコボコにされたわけですよ(笑)。
それで、これはちょっといくらなんでも理不尽だなと思って。渋谷公会堂だったんですけど、坂を下りてきたらNHKの手前に、昔は渋谷ビデオスタジオという撮影スタジオがあって。そこで俳優の養成所みたいなことをやっていて、『役者やる人を求む』みたいな結構大きな貼り紙があったんです。
それを見て衝動的に、『そんなに表方の言うことが絶対で、裏方が言うことが理不尽に扱われて潰されて生きていくぐらいだったら、表方になってやろう』と思って。若かったので、その勢いで渋スタに入って行って、その事務局の人にすごい勢いで事情を話したわけです。
それで、『僕を入れてくれないだろうか』って言ったら、『じゃあ、手続きをここでやって。でも、これぐらいお金がかかるよ』って言われて。『そんな金ないですよ』って言ったら、『じゃあ、出世払いでいいから、僕が立て替えてあげるから。君は多分何とかなりそうだから、とりあえず来てみなさい』って言ってくれたので、そこに通うことになったんです。
特殊効果の仕事をスパンと辞めて、そこの養成所というかワークショップに週2回、半年間通って。それで(養成期間が)終わるときに10分か15分ぐらいの自分のプロフィルビデオみたいな作品をプロのスタッフが撮影してくれて。それを自分の宣伝材料として、自分で売り込んでいけばいいんじゃないかみたいな感じで。
自分は、それまで映画もテレビもそんなに見たことがなかったんです。うちはあまりテレビを見ない家だったんですよ。見るのはオヤジが帰って来たときに野球中継がやっていたらそれを見るくらいで。それ以外に見てもいないのに音が鳴っているのを親が嫌っていて、『見るなら見ろ、見ないんだったら消せ』という感じだったので。
だから、学校で同年代が盛り上がっているような流行(はや)りのドラマとかもあまり見たことないし、そのぐらいむしろ遠い環境にいたんですけど、本当に偶然の成り行きで『表方になりたい』と思ったんですよね。
まあ実際なってみれば、どちらが偉いとか上下じゃなく、単に持ち場の違いでしかないのですが、あのときは衝動しかなかったから。
でも、自分がすごく後れを取っていることは十分自覚していました。周りはみんな『子どものときから映画が好きで映画館に通って役者になりたいと思っていた』とか、『ドラマが好きで連ドラに出たい』とか、基本そういう人がほぼ全員という環境のなかで、圧倒的に自分だけ何を言っているのかわからないという状況だったので、そこからいろいろな作品を見るようになりました。
とは言っても、埋め切れないというか、いまだにコンプレックスみたいなものはあります。僕らの世代で仕事をやり続けてこられている人って、やっぱりものすごく映画愛が強いというか、詳しい人がたくさんいるので。
だからむしろ自分はわからないことを自覚しているので、たとえば何か映画を見た後、どう解釈していいのかわからないなみたいなときに、そういう詳しい人たちに電話して聞いたりして。そういう見方もあるなとか、そういう捉え方で自由でいいんだとか、そうやって後れを取り戻していっている感じです」
※大西信満(おおにし・しま)プロフィル
1975年8月22日生まれ。神奈川県出身。初主演映画『赤目四十八瀧心中未遂』で、第58回毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞、第13回日本映画批評家大賞新人賞受賞。2008年、『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程(みち)』以降の若松孝二監督全5作『キャタピラー』、『海燕ホテル・ブルー』、『11・25自決の日 三島由紀夫と若者たち』、『千年の愉楽』に出演。『祖谷物語 おくのひと』(蔦哲一朗監督)、『BOLT』(林海象監督)、『柴公園』(綾部真弥監督)など出演作多数。映画『東京ランドマーク』が新宿K’s cinemaにて公開中。
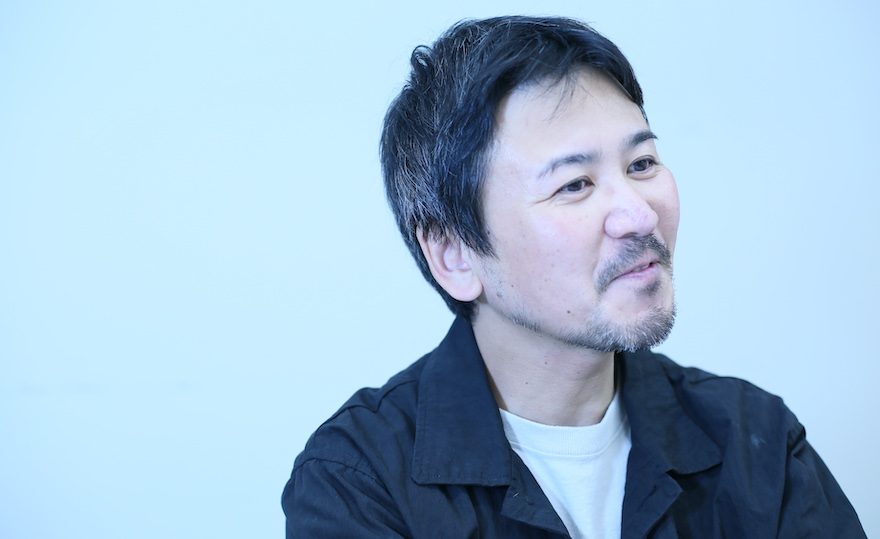
◆原田芳雄さんとの出会い
半年間の養成期間が終わったものの、仕事がすぐにあるわけもなく、芸能事務所のこともよくわからなかったという。
「どうしたらいいかまったくわからなかったので、レッスンのお金を立て替えてくれた事務局の人に相談したら、指導しに来ていたプロデューサーのひとりに『お前みたいなやつは、もしかしたら原田芳雄さんが気に入ってくれるかもしれないから、紹介とかそういうことじゃなくて、自分で手紙を書いて、今日撮った卒業制作のビデオも事務所に手紙と一緒に送ってみたらどうか』って言われたので、その通りに手紙を書いてビデオと一緒に送ったんですよね。
そうしたら、ほどなくして連絡があって、原田家に来るようにと言われたので、指定された日に行ったら、もう大宴会をしているわけですよ」
――原田さんのお宅での宴会は有名でしたね。
「そう。20人ぐらいいろんな方が来ていました。でも、自分はてっきり面接みたいなことがあるのだと思っていたので、履歴書みたいなものを用意したりして行ったのですが、まさかの宴会で(笑)。ポカンとして立っていたら、『そこの若いの、皿片付けろよ!』みたいな感じで怒られたりして、お皿を替えたりしていたんですよ。
それで、みなさんが帰った後、『あれ?そういやお前、初めて見る顔だな』みたいな話になって(笑)。実は呼ばれたから今日来たんですって言ったら、『そうか、そうか。じゃあ明日からうちに来い』ということになって。
とくにちゃんと話したわけでも何もなく、案外すんなり芳雄さんの事務所に所属させてもらうことが決まって、そこから初めて俳優らしい活動をするようになって、芳雄さんの現場に運転手というか付き人で入ったときに初めてプロの現場を経験しました。
初めて会った俳優さんが芳雄さんだったので、そこから猛勉強するわけですよね。入ってから焦って映画館に行って、特集上映を見たりして勉強というか、自分の中の足りなかったものをどんどん埋めていっている時期に、芳雄さんの家に連日いろんなお客さんが来て宴会をやるわけですよ。
そのなかにのちに仕事をすることになる若松孝二監督とか、荒戸(源次郎)さんや(林)海象さんもそうだし、ちょっとずつご縁ができていくというか。初めは、『芳雄さんとこの若いの、お前名前なんだっけ?』みたいな感じでしたけど、何回か顔を合わせているうちに名前を覚えてもらって。
その間、いろいろ話せばそれだけでも5時間、6時間かかっちゃうんですけど、そのなかから荒戸さんが、『今度俺、映画を撮るから芳雄さんのところを離れて俺の事務所に来ないか』っていうことになったんですね。
それで芳雄さんに、『荒戸さんに、この事務所を辞めてその映画の準備のために荒戸さんの事務所に行くように言われたんですけど、どうしたらいいですか?』って聞いたら、『それはチャンスだから行ってこい。こっちのことは気にするな』って言ってくれたんです」

◆主演俳優なのに自ら劇場に飛び込み営業も
原田芳雄さんの事務所を辞めて荒戸源次郎さんの事務所に入った大西さんだったが、すぐに映画製作というわけにはいかなかったという。
「荒戸さんの事務所と言っても人もいないし、何もないんですよ。ただ、そこから毎日、朝の5時とか6時とかに『コーヒー飲もうか』って電話がかかってきて、5時ぐらいからやっている喫茶店が近くにあったので、毎朝コーヒーを一緒に飲んでいました。
荒戸さんは、いつも新聞を読んでいるんですよ。で、何か話があるだろうと思って座っているんですけど、ずっと新聞を読んでいて、何か一言二言、『今日は寒いね』とか言って、コーヒーを飲み終わると、『じゃあ、また』って帰っちゃうので、『これは何なんだろう?』って(笑)。
それで夜になると、今度は『ご飯を食べに行こうか』って電話がかかってきて。夜は夜で何かつまみながら酒を飲んで…というのが1年ぐらい続いたのかな。とくに何かの話をしたとかそういうことではなく、何気ない会話をしていくなかで、徐々に映画の準備も始まって。
そして映画製作の拠点として新たに物件を借りて、人も何人か入ってきて、徐々に映画らしく動いていって、ロケハンをしたり、資金集めのための企画書を書いたりとか。それで、どんどん人が入ってきてはどんどん辞めていって。
今の時代と違って荒々しい雰囲気があったので、合わない人はすぐ辞めていく。で、その同期の中で残っているのが大森立嗣監督だったり、プロデューサーの村岡伸一郎さんだったりするわけですよ。
で、映画作りが始まって、休みなしで毎日。1年のうち元日と、あともう1日ぐらいだけオフで、それ以外はずっと撮影後も含めれば3年ぐらい毎日顔を合わせていました。それで、どこかの段階で、『じゃあ、お前これ主役だ』って言われたので、そういうことになったんだって。
この本を読めとか、こういうことを練習しておけとか、いろいろ言われていくなかで、もしかしたらそういうことかなと思っていたし、その野心がなければ自分も続かなかったと思うんですけど」

大西さんは、2003年に公開された映画『赤目四十八瀧心中未遂』(荒戸源次郎監督)で初主演を果たす(当時の芸名は大西滝次郎)。大西さんが演じたのは、この世に自分の居場所がないと思い尼崎にたどり着いた主人公・生島与一。古いアパートの一室で、焼き鳥屋で使うモツ肉や鶏肉の串刺しをして生計をたてることに。やがて与一は、背中一面に刺青がある女・綾(寺島しのぶ)と関係を持つようになり、心中しようとするが、死にきれず…という展開。
――撮影はいかがでした?
「それはそれでハードでしたよね。今と違って35ミリの時代だったので、セッティングにもものすごく時間がかかるし、まだ昭和の残滓(ざんし)というか、現場の荒々しい気風もあったので。自分が一番の新人で、しかも主演ということだったので、あらゆる部署からボロカスに言われていました。
どうにか撮影が終わってようやく休めるかなと思ったら、クランクアップの翌日から今度は映画の公開準備の段階に移ってくるわけですよ。全部自分のところでやるので、今度は、映画館はどこでやろうかというところから始まって。
『この映画のイメージに合う映画館をみんなリストアップして』と言われてリストアップしたら、『企画書を持って映画館に飛び込みで行くんだ』って言われて実際に行きましたよ。結局ポレポレ東中野と、今はもうないですけど横浜日劇に決まったのですが、今みたいにデータで渡したりできないから、自分たちで重いフィルムを担(かつ)いで行って決めてもらって。
もちろんそれは自分の力とかじゃなく、やっぱり大前提として荒戸さんという名前がまずあって、他にも大楠道代さんだったり、内田裕也さんだったり、寺島しのぶさんたちの存在があったから決まって。
あの当時は、たとえば企画書だって、今だったらパソコンで文字を打ってプリントアウトするんですけど、そんなのあの頃には許されませんでした。『一番いい和紙を探すように』って言われて、浅草の問屋みたいなところで一番いい和紙、しかも破れにくくてインク滲みしないやつとか、それを宣伝美術の人が中心になって一緒に探して。
企画書を作るだけでもそれぐらい手間がかかっていて、ちょっとでも雑なことがあったら罵倒されたし、『そんなんで映画を作れると思うなよ!』みたいな感じでした。
でも、芝居云々というよりかは、むしろその前も後も、企画・製作から上映まで全部ワンセットで映画作りだというのが僕の最初の体験だったんですよね。だから、いまだにそういうことが気になってしまいます」
――『赤目四十八瀧心中未遂』には結局5、6年は関わっていたことになりますか。
「そうですね。上映が終わるまで含めたらそれぐらいかかっています。撮影自体は延べで60日ぐらいですけど、季節ごとの撮影があり、ほとんどが夏の撮影ですが、冬と春にも撮影して、秋は実景だけでしたが、ほぼ1年かけて撮影しました。
その前と、公開してからも1年ぐらい、ポレポレ東中野から始まって、テアトル新宿に行ったり…毎週のように舞台挨拶をしていましたからね」
――大西さんは、この作品で第58回毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞も受賞されました。受賞を知らされたときはどう思われました?
「もちろんうれしいんですけれども、あまりよくわかってなかったというか(笑)。後からその重みというか、いろいろ実感しましたけど、その当時はひたすら日々に追われて精いっぱいという感じでした。賞をもらって、次の日休みになるんだったらうれしいけど、関係ないですからね(笑)」
――荒戸さんからは何か言われました?
「もちろん喜んでくれましたけど、ただ、自分以外の共演者の先輩方がもっと賞をいろいろ受賞されていたので、そういうなかにいると、自分なんか大したことないなっていう風に思ってしまう自分もいて。
『赤目』を撮り終わって公開して解放じゃなかったんです。今度は大森立嗣監督の『ゲルマニウムの夜』の準備が始まって、撮影が始まって。
自分は『ゲルマニウムの夜』に関しては現場に行ったりはしないですけど、みんなが東北のほうで撮影しているときに、東京でデスクみたいなことをやっていて、いろいろ連絡係みたいなことをしたりしていました。
さすがに携帯はあったけど、データで転送とかもできないし、何か足りないから送ってくれみたいなことだったり、お金の管理でも、現場が回らないからどうにか作ってきて、プロデューサーの人とやり取りして…とか。
自分は『赤目』の後、映画に3年ぐらい出ていないなって思って。自分としては、俳優がやりたくてせっかく映画にも出たのに、結局またこういう状態がずっと続くのかなと思うと、何か違うなって。それで、『僕は俳優がやりたい。専念したいです』と言って、映画製作会社じゃない普通の芸能事務所に所属することになりました」
事務所の移籍後、初のオーディションが若松孝二監督の映画『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程(みち)』。以降、大西さんは、若松監督の遺作となった『千年の愉楽』まで晩年の若松作品全5作に出演することに。次回はその撮影エピソードなども紹介。(津島令子)

©Engawa Films Project 2024
※映画『東京ランドマーク』
新宿K’s cinemaにて公開中
2024年7月6日(土)より名古屋シネマスコーレ、大阪第七藝術劇場にて公開予定
配給:Engawa Films Project
監督:林知亜季
出演:藤原季節 義山真司 鈴木セイナ 浅沼ファティ 石原滉也 大西信満 ほか
2008年に柾賢志、毎熊克哉、佐藤考哲、林知亜季の4人で結成された映像製作ユニット「Engawa Films Project」が手がけた初長編作品。コンビニのアルバイトで生活をするミノル(藤原季節)の家にいつものように遊びにきたタケ(義山真司)は、家出をした少女(鈴木セイナ)をミノルが匿っていたことを知る。少女の名前は桜子。タケは未成年である桜子を早く家に帰そうとするが、桜子は帰るそぶりを見せない。ミノルが桜子を匿う理由は何なのか。なぜ桜子は家出をしているのか。3人の不思議な関係が始まる…。












