俳優・中村優子、0歳の娘に叩きこまれた「人生はアドリブの連続」 仕事観にも変化「子どもとの時間を割いてまで、この作品をやりたいのか?」

初主演映画『火垂』(河瀬直美監督)でブエノスアイレス国際映画祭主演女優賞を受賞し、映画『クヒオ大佐』(吉田大八監督)では、銀座のクラブに素性を隠して約1カ月間体験入店し、最終的には指名を受けるまでになった中村優子(なかむら・ゆうこ)さん。
徹底した役作りで知られ、『鉄男 THE BULLET MAN』(塚本晋也監督)、『ユンヒへ』(イム・デヒョン監督)、『燕は戻ってこない』(NHK)などに出演。
◆世界中から優秀なスタッフが集結
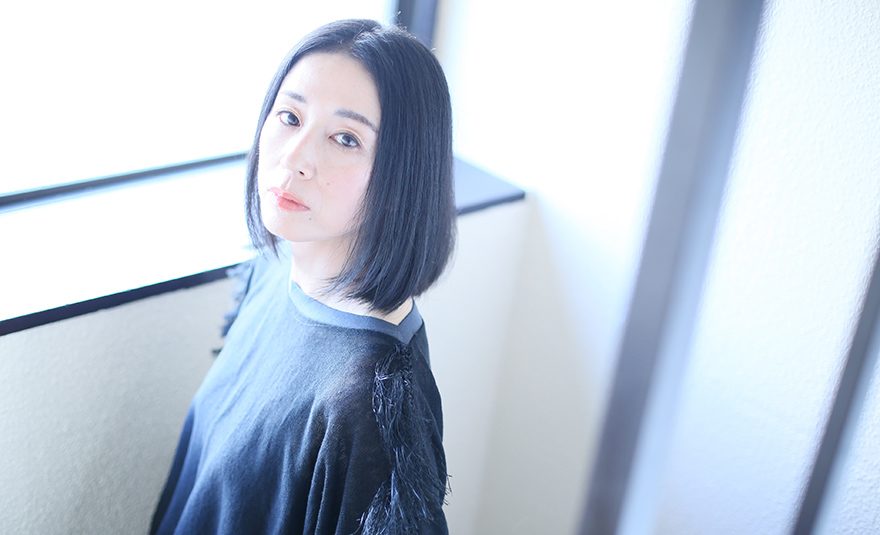
2010年、映画『鉄男 THE BULLET MAN』に出演。この作品は、世界中にカルト的ファンが多い塚本晋也監督が、自身の代表作『鉄男』(1989年)をまったく新しいストーリーで再構築したもの。
東京で日本人の妻と息子と3人で暮らすアンソニーは、ある日突然、目の前で何者かに息子を殺害されてしまう。そして息子を亡くした怒りの感情を抑えられなくなったアンソニーのからだに変化が生じ、徐々に鋼鉄の塊になっていく…という展開。
中村さんは、アンソニーの亡くなった母親で、夫とともに「鉄男プロジェクト」に取り組んでいた研究者・美津枝役を演じた。
――撮影はいかがでした?
「塚本さん(監督)がスタッフを募り、世界中からボランティアや、『塚本組に携わりたい!』という方々が集まったんです。映画の現場は初めてという方や、若いスタッフも多く、手探りな部分もありましたが、少数精鋭の素晴らしいチームで刺激のある現場でした。
それでまた塚本さんのお人柄も本当にステキなんですよね。撮影は結構タイトなスケジュールだったんですが、あるとき貴重な撮影休みが1日あって。
その休み明け、現場にディズニーランドのお土産がさりげなく置いてあったんです。スタッフさんづてに、塚本さんがご家族と行かれていたことを知りました。過酷なスケジュールのなかでもご家族との時間を大切にされていて。
この映画は、家族の物語でもありますから。監督ご自身の中に映画の芯を垣間見ることができたようで、モチベーションも信頼もさらに高まりました」
――中村さんは、塚本監督と映画『野火』でもご一緒されていますね。第二次世界大戦後、フィリピン・レイテ島から帰還した主人公・田村一等兵(塚本晋也)の妻役でした。
「はい。『野火』も私の中ではすごく重要な作品です。というのは、自分はきっと戦争映画に出ることはないだろうと思っていたんです。
実家にご先祖さまの写真が数枚飾ってあるんです。その中に、軍服を着た男性と、スーツを着た男性の写真が二枚、並んでいて。子どもの頃はそれが誰なのかほとんど気にしたことがなかったんですが、あるとき、その写真はどちらも同一人物で、戦死した私の祖父だと知ったんです。
スーツを着ているのは、戦争に行く前の姿で穏やかな表情をうかべているのですが、軍服を着た写真は顔から柔和さが消えてしまっていて、まったくの別人のようで…それがすごくショックだったんです。
戦争がなければ、妻とともに孫たちとも時間を過ごせたかもしれない。戦争が奪うものを、自分の身近に強く感じた瞬間でした。
だから戦争映画には軽々しく出ることはできないと思っていたんですが、『野火』のお話をいただいて、塚本さんの長年の思い、そして『今撮らないといけない』という強い意志を知って、これ以上ない反戦映画だなと。これは私の意思表示としても、ぜひ参加させてほしいと思いました」
――戦争から帰ってきた夫を見ている絶望的な表情が印象的でした。今のおじいさまに対する思いと重なりますね。戦争がなかったら…と。
「そうですね。その後もずっと、その先何世代をも蝕(むしば)んでいくのが戦争。塚本さんの言葉をお借りしますが、『劇中で内臓が出ていたりする描写がグロテスクだという声もありますけど、本当の戦争はこんなものじゃないですから』。
戦争をしてはいけない、というのは当たり前のことなのに、今でも起きているこの現実に危機感を覚えています。悔しいし苦しいです。だからこそ、塚本組の『野火』に参加させていただいたことを、心から感謝しています」
◆「子ども産むぞ!」というセリフが予言に?

2012年には『ギリギリの女たち』(小林政広監督)に出演。この映画は、東日本大震災を機にニューヨークでダンサーをしている長女・高子(渡辺真起子)、東京で暮らす主婦で次女の伸子(中村優子)、1人で家を守り続けていた三女の里美(藤真美穂)が再会。3姉妹それぞれ互いに傷つけ合いながら、思いをぶつけ合うことに…という内容。
――全編わずか28カットで、冒頭35分間がワンカットで撮影でしたね。
「撮影中はそこまで意識していなかったんですが、今振り返るとすごいですよね。ずっと小林さん(監督)の作品に出演したかったので、機会をいただけてとてもうれしかったです。
小林さんの現場はすごい緊張感があるんです。ワンカットだからこその緊張感というわけでもなく、常にピンと張り詰めている。それは役者にとってはすごく気持ち良かったりもするんですが。空気までもが研磨されるような、自然と背筋の伸びる、そんな現場でした」
――3姉妹みんなそれぞれ痛み、問題を抱えていて。
「そうですね。3人が3人とも、それぞれ人生に傷を負っていて。震災で深い傷を負った故郷に、吸い寄せられるように帰ってくるんです」
――「子ども産むぞ」というセリフの通りにお子さんをご出産されて。
「そうなんです。ちょっと予言みたいなタイミングで実際に出産しました(笑)」
――お子さんができて変わりました?
「はい。変わらざるを得なかったです。たった今静かに寝ていたと思ったら、泣いてお呼び出しの繰り返しで。まず、自分の食事なんかは、わずかなチャンスを狙ったスピード勝負でしたね(笑)。立ったままなんてこともしょっちゅう。
『水が飲みたい』『トイレに行きたい』というような細々した欲求は、ことごとく跳ね返される日常で。人生は予定通りにはいかない、アドリブの連続だと、0歳の娘に叩き込まれました(笑)。
忘れられない記憶があるんです。ある日、小さな我が子を見て、急に『取り返しのつかないことをしてしまった』と感じて。それはもちろん後悔ではなく、おそらくは自分の命よりも大切なものがここにいるという事実が、怖くて、怖くてたまらなくなったんです。
でも、そんな大切なものがこんなにも頼りなげな生き物で。この小さな命の、はかりしれない大きさを思って、愕然としました。でも同時に、『可愛いけど、何だこの変な宇宙人は!?』みたいな、今の状況をおもしろがれる自分もいて(笑)。ジェットコースターみたいな日々でしたね」
――お仕事はセーブされたりしていたのですか?
「いいえ、そもそもそんなにたくさんお仕事をするタイプではなかったので。ただ、どうしても現場に入ると子どもといられる時間が少なくなるので、『この子といる時間を割いてまで、私はこの作品をやりたいのか?』というハードルは上がりました」
2019年には映画『ユンヒへ』(イム・デヒョン監督)に出演。この作品は、韓国と日本に生きる2人の女性が心の奥に封じてきた恋の記憶を叙情的に描いたもの。
中村さんが演じたのは、韓国でシングルマザーとして高校生の娘・セボムと暮らすユンヒ(キム・ヒエ)と20年前に恋をして、現在は日本で伯母(木野花)と暮らしているジュン。かつての母の恋を知ったセボムは、ひそかに2人を会わせようと計画をたてる。
「『ユンヒへ』は生涯の1本ですね。ありのままの自分を尊重して、ありのままの他人もまた尊重する。その尊さを、教えてくれた本当にかけがえのない作品です。
セリフにもありましたが、『どんな形の愛があってもいい』。ジュンを生きることで、その視点をもらえました」
――ユンヒのセリフに「あとの人生は罰だと思っていた」というのがあって胸に突き刺さりました。どんな思いで生きてきたのかと思うとつらいですね。
「そうですね。当時の社会は、マイノリティの人々にとって息もできないような窮屈な世の中でした。アイデンティティを否定して生きることは、想像を絶する苦しみがあったと思います。
でも、ユンヒの娘であるセボムが、その報われなかった愛を救うきっかけとなって。まさに新しい春が来て、時代が変わっていく希望を感じます。
ちゃんと自分の母を知ろうとする。セボムは、ユンヒを母という役割に閉じ込めないんですよね。逆に、思いがけず知ってしまった、母である前の一人の人間としての彼女を知りたいと思う。セボムには、他者を尊重する資質がすでにあるんです」
――撮影前にキム・ヒエさんの高校時代のお写真を送ってもらったそうですね。
「はい。20数年前からずっとジュンの心の中にはユンヒがいる。その当時のユンヒはどうだったのか。どうしてもお顔が見たいと思って、韓国のプロデューサーさんにお願いしてヒエさんに高校時代のお写真をいただきました。
そのお写真を見ながら、2人はかつてどんな風に過ごしていたのかなどいろいろ想像していました。今も大事にとってあります」
◆役者の糧にと「能」の世界へ

©2024 The Box Man Film Partners
※映画『箱男』全国公開中
配給:ハピネットファントム・スタジオ
監督:石井岳龍
出演:永瀬正敏 浅野忠信 白本彩奈/佐藤浩市 渋川清彦 中村優子 川瀬陽太
現在、映画『箱男』が公開中。カメラマンの男(永瀬正敏)は、ダンボールを頭から被り、一方的に世界を覗き見る“箱男”に心を奪われ、自らも箱男としての一歩を踏み出すことになるが、数々の試練と危険が襲いかかる…という展開。
この映画は、1997年に映画の製作が決定し、スタッフ、キャストが撮影地のドイツ・ハンブルグに渡ったものの、クランクイン前日に撮影が中止になってしまった幻の企画が27年の時を経て実現したもの。
「この作品に参加できるということが奇跡のようでした。『箱男』がまた始動したというニュースを知って、一映画ファンとして必ず劇場に行こうと思っていたんです。
監督が石井岳龍さんで、主演は永瀬正敏さん。そして浅野忠信さんに佐藤浩市さん。日本映画を牽引し続けていらっしゃる憧れの先輩方。公開を楽しみにしていたら、キャスト候補になっていると伺って、本当に驚きました。
原作を最初に読んだのが20歳くらい。当時のカオスなイメージしか記憶に残っていなかったので、もう一度原作を読み返したら、現在のネット社会の預言書のようで。とても衝撃を受け、夢中で読みました。
女刑事は原作にない役だったのですが、妄想世界の中のキャラクターで。これは本当に石井さんの映画でしか存在し得ない役です。私はなんて幸運なんだろうと(笑)。
妄想の中の登場人物だからこそ、どんな居方が求められているのか、というのがまず気になって。石井さんからは『フェイクだけど、あくまでもリアルに。リアリティを持ったお芝居をしてください』とのリクエストをいただいたので、警察関係のドキュメンタリー番組などをたくさん見て参考にしました。
いろんな世界を知ることができるというのは、すごく貴重ですよね、おもしろい。この仕事の醍醐味だと思います」
――『箱男』は、27年前にスタッフ、キャストがドイツに集合し、明日クランクインだという前日に撮影中止になったそうですね。
「はい、そう伺っています。そのときの皆さんの無念たるや…胸が痛みますね。でもそれが時を経て、当時よりも格段に“箱的社会”となった2024年に公開されるという巡り合わせ…。『箱男』のドラマチックな運命に拍手を送りたいですね」
2024年、4月~7月に放送された『燕は戻ってこない』(NHK)に出演。このドラマは一生懸命働いても月収14万円で貧困生活から抜け出せない29歳のリキ(石橋静河)が、さんざん迷った末に高額な謝礼と引き換えに、元バレエダンサーの草桶基(稲垣吾郎)とその妻・悠子(内田有紀)の代理出産を引き受けることにするが、さまざまな予期せぬ出来事が…という顛末を描いたもの。
中村さんは悠子の親友でリキをアシスタントに雇い、自身が所有する屋敷(シェアハウス)に住まわせてあげる春画画家・寺尾りりこ役を演じた。
「撮影に入ってほどなくして、りりこは原作者である桐野夏生さんのお気に入りのキャラクターだと、人伝に耳に入りまして。『ええ!どうしよう!』と。でも、プレッシャーを感じようが感じまいが、結局は私の“りりこ”しかできないなと、腹を括(くく)ってどうにか雑念を払いましたね(笑)。
劇中では強く印象に残っているセリフがふたつあって。ひとつは、3話での居酒屋のシーンで『自分は家族制度から抜け落ちるアンチだから、こういうアンチ人間が世の中の常識に疑問を投げかけていかないと』という悠子への言葉。それにすごくドキッとして。
りりこや『ユンヒへ』のジュンのように、“普通”から外されてしまった人は、生きていくなかでアイデンティティを揺さぶられ、常に自分自身の視点を意識せざるを得ないわけで。
では、マジョリティ側の人間はどうかと。もしかしたら、多数派であることに安心し切っていろんなことを見落としているかもしれない。ハッとしました。このセリフはこの先もずっと忘れちゃいけないと。
もうひとつは『私の絵は誰かのために描いているのではない』というセリフ。これはもう、自分の心を代弁してもらったようでしたね。私自身、演じるということをかつて誰かのためにやったことがなくて。
そもそも『なぜ私は、お芝居をするのか?』『なぜ私はこの物語に、この役に惹かれるのだろうか?』と。わからないから、それが知りたい。演技という手段を通して、人生を知りたいのかもしれません」
――中村さんは、「能」もやってらっしゃるのですか?
「はい。早いもので、もう20年続けています。大学を卒業する頃から、役者の糧になるような、それも身体表現的なものを何かひとつやりたいと思っていたんですね。
それで、日本舞踊の見学に行ったりとか、色々なダンスのクラスをちょこちょこ覗いていたんですけど、なかなか出会いがなくて。
そんなときに、フランスでコーポリアルマイム(役者の身体表現を追求したフランス発祥の表現形式)の勉強をしていた友人が、帰国してから『能』をはじめたと聞いて。彼女の話しぶりからすごく『能』に興味がわいたんです。それで、ちょうど彼女の師匠の舞台があるから見に行かないかと誘われて。その舞台で、雷に打たれました。『これだ!』と。
師匠は、金剛流の宇高通成先生という、国の重要文化財(重要無形文化財総合指定保持者)の方だったんですね。でも、何もわかっていない私は、抑えきれない情熱で押し掛け弟子入りを果たしました(笑)」
――いきなりそういう方はなかなかいないでしょうね。
「先生はおもしろがってくださったのかなと思います。私は普段、優柔不断な面も多々あるのですが、『これだ!』というものがあると、大胆かもしれませんね。
空の状態でその場に立つこと、自我から自由になること…まだまだ未熟ですが、お能から受ける影響ははかりしれず、あのとき直感に従った自分を褒めてあげたいです(笑)」
端正なルックスに加え、万全な準備と大胆な決断力も魅力。今年は『箱男』のほかに『碁盤斬り』(白石和彌監督)、『彼方のうた』(杉田協士監督)、『違国日記』(瀬田なつき監督)がすでに公開。中村さんにはスクリーンが良く似合う。(津島令子)
※河瀬直美監督の“瀬”は旧字体が正式表記
ヘアメイク:風間啓子











